こんにちは、たつみです。
今回は認知症についての説明というよりかは、認知症への考え方が変わるきっかけになればと思って書いています。
あまりにシンプルでストレートな題名からわかるように、気持ちの良い内容ではないかもしれません。
むしろ、今認知症のご家族を抱えている方にはきつい内容だと思います。
そのような方に向けた記事であるとはいえ、無理に読む必要はありません。
少し気持ちが落ち着いて読んでみようかと思った時にこの記事を読んでいただけたらと思います。
認知症は亡くなる病気なの?

認知症で亡くなる?
認知症はもの忘れの病気だろ?
ものを忘れるからってなんでそれで亡くなることになるの?



認知症はもの忘ればかり言われますが
根本的には脳の機能全体が落ちる病気です。
以前「アルツハイマー型認知症とは?症状や特徴をやさしく解説します」という記事でアルツハイマー型認知症という病気についてお話しましたが、
認知症とは脳にカビのようなゴミが徐々にこびりついて、脳がダメージを受けるという病気です。
この脳がダメージを受けるというのは、ダメージの受け方が違うだけでどの認知症でも同じです。



他に脳がダメージを受けるご病気といえば何が思い浮かびますか?



え、えーと…脳出血とか脳梗塞とかかな?



そうですよね。ではそのような病気になったら何が怖いですか?



それは〜、麻痺が残ったり、最悪亡くなること…かな?



そうですよね。
認知症も同じなのです。
正確には認知症で麻痺のような状態になることはほとんどありませんが、徐々に全身の機能は落ちてきます。
そう、認知症で落ちるのは認知機能だけではありません、運動機能、嚥下機能(飲み込みの能力)、全身の臓器の機能低下等、その症状は全身に現れてくるのです。
介護保険の説明をしました、介護保険の内容のほとんどは脳機能の維持というよりも落ちた身体機能に対してのサポートだったはずです。
歩けなくなってきた方の身体リハビリ、杖や電動ベッドのレンタル、自宅で生活を送れなくなった人の特別養護老人ホームでの入浴や排泄介護。
想像してみてください。もの忘れをするようになっただけで、歩けなくなると思いますか?
これこそが認知症の怖さです。
要介護の人の余命は短い
前回、前々回と介護保険で受けられるプランについてお話しました。
要介護の方は要支援より、より重症で日常生活を維持するために人の手助けが居る方であるとお伝えしました。
精神科で多くの認知症患者さんをみていると、大体初診時の印象で患者さんの状態が要介護か要支援かは予想がつきます。
そして要介護に相当する患者さんが入院する時には、自分は「最期の時の迎え方」のお話をするかどうかを患者さんやご家族様の様子をみてお話するかどうかを考えます。
なぜなのか。それを今からお話します。
要介護の方の最期の時は近い
よく医療ドラマでは「もってあと数年です。」というふうに主治医の先生が話しをしている場面があります。
どうやって医師はそれを判断しているのか、いわゆる余命の判断の指標に使うのが「5年生存率」です。
5年生存率とは読んで字の如く、「5年間生き延びることができる確率」です。
要支援の方の5年生存率は約70%です。つまり「10人中7人は5年間は生きていられる」可能性が高いということになります。
では要介護の方はどうでしょうか。
要介護の方の5年生存率は約20%です。つまり「5人中4人は5年以内に亡くなる」可能性が高いということになります。
どうですか、この数値をみて認知症は亡くならない病気とは思えないですよね。
要介護度が上がるにつれてその余命は短くなってきます。要介護度5の最重症度の方の平均余命は1年2ヶ月です。
認知症の方の最期の経過
認知症の方の最期は大体みなさん肺炎で亡くなることが多いです。あるいは食事そのものを取らなくなることで脱水や低栄養で亡くなることも多いです。
この肺炎がよく巷を騒がせる「誤嚥性肺炎」です。
誤嚥性肺炎とは、食べ物や唾が気管を通って肺の方に向かうことで起こる肺炎です。本来肺の中に食べ物が入ることがありませんが、嚥下機能が落ちた高齢者ではそれが起こります。肺にとっては異物であり、口の中の細菌が肺の中に入るため肺炎を起こします。
体感では精神科病院での認知症で入院した患者さんの7〜8割は誤嚥性肺炎で亡くなります。



でも、肺炎って若い人でも偶になるけど
抗生剤で治ってるじゃないか。
コロナじゃあるまいし治るだろ。



半分正解で半分ハズレです。
1回の誤嚥性肺炎は治せることもあります。
ですが根本は認知症による嚥下機能の低下です。
つまり、どれだけ肺炎を治しても、嚥下機能の低下が改善しない以上、
肺には常に細菌が、つまり肺炎の燃料が常に運ばれていきます。
誤嚥性肺炎が起きた時、自分はご家族には『誤嚥性肺炎とは体の衰えの「結果」として現れる病気です』とお伝えしています。
加えて、この肺炎を治してもまたすぐに肺炎を起こす可能性が高いこと、肺炎治療は体のエネルギーを使うため、エネルギーの枯渇を起こしやすいこともお伝えします。
エネルギーが枯渇していったらどうなるか、最終的には肺炎に抗うことができずに最期の時を迎えます。
誤嚥性肺炎にならなければ亡くならいのか?



じゃあ、もし肺炎にならなければ
認知症でも亡くならないんじゃないのか?



残念ながらそうではありません。
もちろん肺炎になるよりかは長生きであるとは思いますが、
重度認知症の方はいずれにせよ亡くなってしまうことが多いです。
なぜ肺炎を起こしていないのに亡くなるのか、それは「認知症の患者さんは最終的にご飯も食べなくなる」からです。
これは人によります。1、2割は食べる人もいれば、本当に全く食べ物を口にしない方もいます。
その姿はまるで「食べるということすら忘れた」とすら見えるほどです。
ご飯を食べられない状態が続けば、どうしても体力が落ちてしまい、命に関わります。
なぜこんな辛い話をするのか。
気分障害の記事を書いた後に自分が認知症という病気を取り上げたのは、もともとこの記事を書きたいという思いからでした。
精神科病院で認知症の方が入院される時、別れを予想しているご家族は3割もいません。精神科病院に入院して、時間がたったらどこか老人ホームに入れれば良いな〜と漠然と考えている方がほとんどです。
そして入院中に急に別れを意識しなければならくなった時にご家族は動揺し、延命治療をどうするのかの判断を突然迫られます。
その時の判断を後悔する方も少なくありません。何より、最期の時が近いのであればもっと面会に来れば良かったと後悔する方が多いのです。
認知症が亡くなる病気であることを知った時、それで全てが良くなるわけではないのですが、後悔する別れを避けられる可能性は上がるのではないかと思いこの記事を書きました。
今この記事を書いているのは2025年7月、参議院選挙の前です。政党の中では「高齢者の延命治療の是非」に関して政策に挙げている党もあります。
別にそれを狙ったわけではなく、たまたまなのですが、今は日本という国も貧しくなり医療制度そのものを見直す時期に来ています。
次の記事は「高齢者の延命治療に対して」のことを書こうと思います。
皆さんがどのような考えを持たれるか、是非コメントいただけたら嬉しいです。
ではまた。



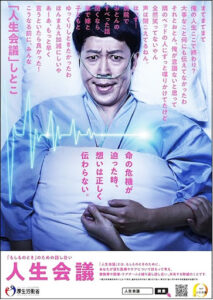




コメント