こんにちは、たつみです。
最近、SNS上でとある診断書が話題になっていました。
僕の質問箱にも「どういう点が問題なのか解説してほしい」といったご質問が届いたので、ここで一つ整理しておくのは良いかなと思います。
今回は、その診断書の内容をもとに、
- 診断書には何が書けて、何が書けないのか
- 話題の診断書にはどんな問題点があるのか
について、精神科医の立場からわかりやすく解説していきます。
この記事はあくまで診断書の記載内容について触れたものです。
被害を受けた方を否定する意図は一切ありません。
今回の一連の騒動に関して、意見を表明するものではありません。
診断書で「書けること・書けないこと」
診断書とは、「医師が診察によって確認できた医学的な事実」を記載するものです。
つまりどういうことかというと、原因→結果の流れが明確なものでないと書けないのです。

よくわからないのだけど。



これだけ言われてもわからないと思うので
簡単にまとめてみましょうか。
〇 書けること
- 症状として実際に確認できたもの
- 医学的に妥当と考えられる診断名
- 今後の治療方針(例:休養が必要、通院中 など)
このように診察室での様子や検査データからわかる症状、その症状からの診断。
その診断に基づいて今後必要な対応、方針について僕らは書くことができます。
基本的に診断書に記載できるのはこれだけと思っていただいて構いません。



逆に次のようなものは書けません。
✖ 書けないこと
- 社会的な出来事との因果関係(例:いじめが原因で○○になった)
- 訴えられている加害者の行為に対する医学的評価
- 医師が診察以外で知り得ない内容(例:いじめの詳細な経過)
このように、「何故この病気になったのか」ということを記載する診断書は基本的に書けません。
たとえば:
- 「うつ病と診断されたので休養を要する」→ 記載できます
- 「職場のパワハラでうつ病になった」→ 基本書けません
このあたりの線引きをイメージとして持っていただけたらと思います。
話題になった診断書とは?
今回話題になった診断書では、あるいじめ被害を受けた方が「右半身が動かない」という症状を訴えたことに対し、以下のような診断書が出されていました。
今回の診断書はこんな感じです。
診断:解離性障害
X年X月X日に複数個所を殴打された後に意識消失・右半身麻痺・感覚障害を呈し入院。検査上は異常所見はないが症状は残存しており、精神的な要因により生じた解離性運動障害・感覚障害と診断した。
診断年:X+10年Y月Y日
この診断書、どこが気になる?
この診断書について、医療者の視点から気になる点を整理してみます。
① 出来事そのものを“証明”しているように読める
「X年X月X日に複数個所を殴打された」
やはりまずここですね。この部分は症状ではなく「診察外の出来事や原因」という部分を断定的な表現で記載しています。
あくまでこれは診察室で患者さんが仰った情報ですので、これを公的な書類の文章に書くのは望ましくありません。
あえて書くのならば、「本人の言うには~」と前置きをして書くのが限界と思われます。
② 因果関係が断定的に書かれている
検査上は異常所見はないが症状は残存しており、精神的な要因により生じた解離性運動障害・感覚障害と診断した。
①の後にこの文章が続くことが極めて問題です。
この文章を医療者が読んだときにどんなふうに言い換えられるかというと



検査上は麻痺を起こすような原因は何もないけど、
本人は体動かないって言ってるし。
体の問題がないならあとは精神的な問題だよね。
やや乱暴ですがこんな感じの印象で取られます。
どうですか、①の文章と続けて読むと、「言ったもの勝ちじゃないか」という印象を受けませんか?
③ 解離性障害の診断名が誤解を招きやすい
「解離性障害」という病名は正式にあるとされる精神疾患です。しかし、かつては「ヒステリー」とも呼ばれ、“作り物の病気ではないか”という偏見を生みやすい診断名です。
ここでは詳しい説明を省きますが、解離性障害の症状は幅広く、患者さんの価値観や性格に影響が大きい病気です。
公的な診断書としては「嘘じゃないか?」であったり「それは貴方の問題なんじゃないの?」という風に取られてしまう可能性があり、患者さんが軽んじられてしまう可能性があるのです。
この診断書が広がったことの懸念
このような診断書が広がることで、
「精神科の診断書って、訴えれば何でも書いてくれるの?」
というような誤解を持たれてしまうことがあります。
そしてその結果、
- 無理な要求が増えてしまう。
- 精神科の診断書全体が信頼されにくくなる
- 本当に必要な診断書までも疑われる
- 解離性障害をもつ人々への偏見が強まる
という、誰も幸せにならない現実が生まれてしまうのです。
じゃあ医者は患者の言うことを信用してないの?



実際に起きたかわからないから書けないってことは、
先生たちは患者の言う事を信じてないってこと?



それは違います。
僕らは基本的に患者さんの言う事を信用して
診断、治療を行います。
僕らは患者さんの言う事を基本的に信用します。
ただしこれは「患者さんと医師の間だけ」で成立します。
しかし診断書というものは、僕ら精神科医が、患者さんの状況を社会にお伝えするものです。
ほかの方が関わってくる以上、その内容に誤りがあってはいけないのです。
じゃあ実際に被害を受けたらどうしたら良いの?



じゃあ、どうしたら良いの?
本当に被害にあったのに、それを証明できないなんて・・・



もちろん、そのお気持ちは当然です。
その場合は病院ではなく司法機関へ相談しましょう。
医療では出来事そのものの証明や、加害行為の有無は判断できません。
ですから、「被害を受けたことを明らかにしたい」「法的な対応をしたい」と考えている場合は、警察・弁護士・児童相談所など、司法的な機関への相談が必要です。
被害を“なかったこと”にしないためにも、しかるべき機関に相談することが、結果としてご自身やご家族を守ることにつながります。
おわりに
「診断書を書いてもらえたら、自分の苦しみが認められるかもしれない」
そう思って受診される方はたくさんいらっしゃいます。
でも、精神科の診断書にはどうしても限界があります。
特に因果関係の証明は、精神科にとって非常に難しいテーマです。
だからこそ、「書けない」とされる内容があったとしても、
それは決して、あなたの気持ちが軽んじられたわけではありません。
今、求めている書類が「何のためのものなのか」をもう一度考えて、
医療だけでなく、司法・行政などの力も活用していけると良いのではないでしょうか。
今回の記事のように皆さんから頂いた質問に答えるような記事も書いていくつもりですので、聞いてみたいことがありましたら是非ご質問ください。精神科のことじゃなくても大歓迎です。
今更ですが質問箱を開設しました!
— 精神科医たつみ (@tatsu3noseishin) August 27, 2025
疾患や症状についてなどの個人的な質問にはお答えできませんが、気軽にご質問ください!https://t.co/nfeZ0XeAo1で質問を募集しています! https://t.co/Vy5WREBacg
ではまた。




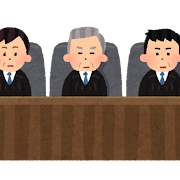



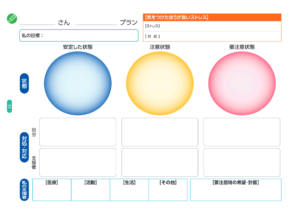
コメント