こんにちは、たつみです。
前回・前々回の記事では、「延命治療とは何か」ということ、そして「自分は基本的には延命治療に反対である」という立場についてお話ししました。
今回の記事では、それらを踏まえたうえで、私自身の考えを少し掘り下げてみたいと思います。
この記事で述べているのは基本的に「高齢者」に対する延命治療の是非についてです。
子どもや若い方に対する治療については、まったく別の話になりますので、ご留意ください
なぜ延命治療が議論されるのか
延命治療に関する議論が盛んになっている背景には、大きく2つの理由があります。
①社会保障制度の限界
医療費の増大により、国の財政は厳しさを増しています。
このままでは、すべての人に同じように医療を提供し続けることが難しくなると懸念されています。
②人としての尊厳の問題
ただ命を長らえさせることが、本当にその人の幸せにつながっているのか。
「どう生き、そしてどのように最期を迎えるか」が問われる時代に入ったと私は感じています。
「むやみに延命治療をすべきではない」という立場
自分は、高齢者に対して「むやみに延命治療を行うべきではない」と考えています。
ぼんやりとした意識のまま、ただ点滴や機械によって外部から命を繋ぐという治療がその人にとって幸せなことかどうか、疑問を感じるからです。

高齢者を見捨てるのか。
今まで頑張ってきた人たちを大事にしないのか。



高齢者は知識の宝庫だ。
彼らの知識と経験を繋がなければならない。



意識もないまま点滴することは「高齢者を大切にすること」ですか?
延命治療中で意識もほとんどない方がどうやって知識を伝えるのですか?
そうなる前にその人の言葉や経験を受け取る時間を大切にすべきではないですか?
自分が行うべきではないと言っているのは「回復の見込みもないのにただ漫然と続けられる治療」です。
後ではなく今のうちに大切な人と過ごしてください
延命治療が必要になってから「もっと話しておけばよかった」「もっと感謝を伝えたかった」と思っても、もう手遅れなのです。
そのとき行われる医療は、「最後の時を迎えつつある人のための医療」ではありません、「あなたのための医療」です。
僕の考えは結局のところ「別れが惜しい人がいるならば、今大事にするべき」ということです。
一定の年齢を超えた延命治療は「自費負担」にするという問題
社会保障の持続性を考えたとき、「一定の年齢を超えた延命治療は自費で行うべき」という意見も出てきています。
たとえば、親が事業主であり、その継承までに時間が必要だという場合、自費で延命治療を選択するのは一つの選択肢だと思います。
しかし、この考えには当然批判もあります。
「お金持ちだけが延命治療を受けられるのか?」
「お金がない人は死ねということか?」
そんなつもりはありません。ですが、現実としてそうなってしまう可能性は否めません。
選択肢があるだけ、まだましなのかもしれません
今のまま社会保障制度が維持できなければ、
「すべての人が延命治療を受けられない」という未来も現実になりかねません。
そう考えると、「お金がある人だけでも選べる」という状況は、まだ“まし”なのかもしれません。
ちなみに、現在の制度であれば、自己負担は1割や3割、さらに高額療養費制度の上限があります。
それによって多くの人が何とか支払えていますが、すべてが“自費”となった場合、ほとんどの方が治療費を払えなくなるでしょう。
これは医師である私たちも同じです。
高齢者はじゃあ何もせずに見殺しなのか
これもまたよくある反論です。



高齢者の延命治療はしないだと?
見殺しにするってことか、それでもお前は医者か。



医療とは延命だけが全てではありません。
穏やかに最後の時間を過ごすための緩和という考え方があるのです。
これがおそらく多くの方が誤解していることなのです。
「延命治療をしない=見殺しにする」と誤解されている方は結構いらっしゃいます。
断じてそんなことはありません!
私は緩和ケアや痛みを和らげる医療については、賛成の立場です。
緩和ケアとは「人が穏やかに最後を迎えるために行われるための医療」であり、
本人の苦痛を和らげ、笑顔でいられる時間を増やす。最後までその人らしく過ごす時間を設けるための治療です。
本当にすごい緩和ケアの先生が診られた患者さんの最後は、びっくりするほど穏やかなものになります。
痛みもなく、本人も家族も笑顔で温かい最後を迎えることができます。
延命治療が、「最後の時間を増やすための医療」とするならば
緩和ケアは、「最後の時間の質を高める医療」です。
自分は、高齢者にこそ、こうした医療が届けられるべきだと考えています。
高齢者医療に制限を設けるべきか
私は、将来的には高齢者医療に一定の制限を設けることも必要だと思っています。
たとえば、
- 骨折や視力障害など、生活の質に直結する病気への対応
- 重篤化を防ぐための予防医療
といった治療は、引き続き行うべきだと思っています。
精神科治療に関しては言葉を控えます。どのような意見であれ、ポジショントークになってしまうからです。
「高齢者はもう生産性が無いのだから」というならば子供も一緒では?
延命治療に関して



高齢者の生産性がないのだからというならば
子供の延命治療はどうなんだ。



それは、安易には否定できない、今後考えていかないといけない意見と思います。ですが、それは次の段階です。
これはよくある延命治療に関しての反論です。
これは、確かにある種その通りで、今後はおそらく議論の対象になる意見ではあるのです。
ですが、私はまずは高齢者医療に焦点を当てて議論すべきだと考えます。
理由は2つあります。
- 延命治療を受ける高齢者の数が圧倒的に多いという現実
- 子どもと高齢者では、社会的・人生的な背景がまったく異なるという点
「子どもも同じでは?」という論点を持ち出すと、かえって議論の焦点がぼやけてしまいます。共通点は誰にでもあるからこそ、「それならこれはどうなんだ?」という形で論点を広げすぎると、かえって本質が見えなくなってしまいます。
この延命治療の問題は倫理の問題と、それ以上に社会保障の制度という現実的な側面があります。
そのような話をする場合はまずは線を引いて焦点を絞って考えるべきです。
そしてその観点に立った時に自分は高齢者の延命治療というところに焦点を当てるべきであると思っています。
おわりに
ここ数回、重いテーマの記事が続きました。
でも、自分もこの機会に改めて自分の考えを見つめ直すことができました。
高齢者医療のあり方は、今後ますます大きな議論になるはずです。
医療制度が変わるとき、少しでも「よりよい方向」に進むよう願っています。
次回は、少し肩の力を抜いたテーマで書けたらと思います。
それでは、また。




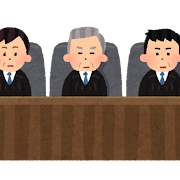




コメント